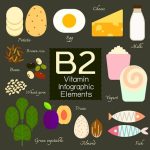食中毒はその種類や重症度によっては命にもかかわる危険なもの。
食中毒を予防するためにもっとも重要なのは「食べ物が食中毒を起こす状態にしないこと」です。
食中毒の基礎知識、実生活で気を付けたいポイントを紹介します。
Contents
食中毒とは

食中毒とは、食中毒の原因となるものがついた食品を食べることにより、腹痛、下痢、嘔吐、発熱など、さまざまな症状を起こすものです。
食中毒はその種類や症状の重さによっては命にかかわることもあるため、まずは予防することが重要です。
食中毒の種類
食中毒は、食中毒の原因になるものによっていくつかの種類に分けられます。
- 細菌による食中毒
- ウイルスによる食中毒
- 有害物質による食中毒(ヒスタミンなど)
- 寄生虫による食中毒(アニサキスなど)
食中毒の事例では、これらのうち細菌やウイルスなどの微生物によるものが多くを占めています。
食中毒を起こす細菌・ウイルス
食中毒を起こす微生物には、以下のようなものが知られています。
| 細菌・ウイルスの名称 | 生息場所(汚染源) |
| 腸管出血性大腸菌O-157 | 人と動物の糞便 |
| カンピロバクター | 人と動物の糞便 |
| ウェルシュ菌 | 人と動物の糞便 |
| サルモネラ | 人と動物の糞便 |
| 黄色ブドウ球菌 | 人の化膿創、手指、鼻汁、乳 |
| セレウス菌 | 土壌 |
| ボツリヌス菌 | 土壌 |
| 腸炎ビブリオ | 沿岸海水、海産魚介類 |
| ノロウイルス | 人の糞便、二枚貝 |
それぞれに生息場所があり、そこから人間の食事に混入することで、食中毒を起こす原因となります。
食中毒が起こる過程
食中毒、特に微生物による食中毒が起こる過程を紹介します。
食品に原因微生物がつく
食中毒の原因となる微生物の多くは自然界に存在しています。
土壌や海水など食材がもともとあった場所や、食材そのものについているものや、ヒトの手や手の傷などに存在するものなど、さまざまです。
これらの微生物が調理前、調理後にかかわらず食品に付着することで、食中毒発生の原因となります。
食中毒の原因微生物が増える、または増殖とともに毒素を生成する
食品についた状態の原因微生物は増殖を始めます。
低温ではあまり盛んに増殖しませんが、30-40℃の温度帯では急速に増殖し、微生物の種類によっては毒素を生成します。
ヒトが原因微生物の増えた(毒素が生成された)食品を食べる
原因微生物が生きた状態で多数存在したり、微生物の産生した毒素が多量に含まれた食品を摂取することで、下痢や嘔吐、腹痛などの食中毒症状が出ます。
食中毒を起こしやすい環境と気候
食中毒の原因となる細菌は5~45℃の温度で増殖しやすい性質を持っています。
特に増殖しやすい温度は30~40℃であり、ちょうど日本の夏場の気温と同じくらいといえます。
そのため、気温の高い夏場は細菌にとって増殖しやすい季節であり、細菌が原因となる食中毒が起こりやすい季節でもあります。
いっぽう、比較的気温の低い冬であっても、食中毒が起こらないというわけではありません。
細菌が増殖しやすい温度で長時間放置されている場合はもちろん、冬はノロウイルスなどによる食中毒が増える時期でもあります。
1年を通して安全な食事を心がけたいですね。
匂い、味、見た目で判断できない
食品が腐敗すると、においや味、見た目に変化が表れるため、こういった変化から食べるかどうかを判断する人も少なくないでしょう。
腐敗というのは細菌などの作用によって食品のたんぱく質などや脂質が分解され、ヒトにとって不快な味やにおいが発生した状態をいいます。
このときの不快なにおいや味は食品由来の物質からできたものであり、食中毒菌を含む細菌そのものに味やにおいがあるわけではありません。
食品を腐敗させる菌が増殖しやすい環境は食中毒菌にとっても増殖しやすい環境でもありますが、腐敗菌の増殖と食中毒菌の増殖は必ずしも同時に起こる現象ではありません。
腐敗を起こす細菌と食中毒菌はイコールではないため、腐敗を起こしていたとしても必ずしも食中毒症状が起こるとはいえず、また腐敗を起こしていない状態でも食中毒が起こることも多くあります。
新鮮な状態であっても生の肉類などにはカンピロバクターなどの食中毒の原因となる細菌が付着しており、においや見た目に問題がなくても食中毒を起こすことがあります。
食中毒の予防三原則

食中毒を起こさないためには、この過程のどこかでストップをかけることが重要です。
- 原因微生物を食品につけないこと
- 原因微生物を増殖させないこと
- 原因微生物を殺菌すること
この3つのポイントを守ることで、食中毒の予防が可能です。
つけない
生肉や手指に通常存在する細菌が食中毒の原因となることがあります。
まずはそのような菌を、食べる状態の食品に「つけない」ことが重要です。
- 生肉等の汚染された食品を生食用の食品と触れさせない
- そのまま食べる状態の食品(生食用の食品や調理済みの食品)を素手で扱わない
ふやさない
少量では食中毒を引き起こさない食中毒の原因微生物も、高温多湿の環境によって増殖すると食中毒の原因となります。
原因微生物が増殖する前に食べきる、または原因微生物が増殖しないように保管方法に気を付けることが必要です。
- 微生物が増えやすい温度帯で長時間放置しない
- 保管するときは冷蔵、冷凍など低温で保管する
殺菌する
熱に強い細菌や毒素もありますが、増える前に殺菌してしまえば最近は死滅して食中毒は起きることはなく、毒素の生成もその時点でストップします。
調理における殺菌は「加熱」が基本です。
- 食材の中心部まで加熱する
買い物から保存までの重点対策ポイント

上記の食中毒予防3原則をもとに、日常生活の中で具体的にどんなところに気を付けるべきかをまとめました。
買い物から調理、保存までの過程を順番に確認していきましょう。
買い物から帰宅まで
買い物中や持ち帰りの過程では、食中毒の原因微生物が存在する食品とその他の食品を触れさせないこと、原因微生物が増えやすい環境に置かないことがポイントです。
- 生ものがほかの食品に触れないように梱包する(つけない)
- 肉や魚などの生ものは保冷剤や保冷バックを活用して低温を保つ(ふやさない)
- 持ち運びの時間をなるべく短くする(ふやさない)
- 帰宅したら速やかに冷蔵庫に入れる(ふやさない)
調理までの保存状態
買い物後にすぐに使わない食材も多いはず。
保存中に微生物が増殖したり、ほかの食品を汚染したりしないよう、保存状態にも注意が必要です。
- 冷蔵庫内で肉や魚の水分(ドリップ)が付着しないよう包む、または保管場所を分ける(つけない)
- 冷蔵庫が低温を保てるよう扉の開け閉めは最小限にする(ふやさない)
- 保存している食材は消費期限内に使う(ふやさない)
調理中

調理中も食材同士の接触には注意が必要ですが、加えて調理器具や手を清潔に保つことも必要です。
原因微生物が手や調理器具を介して広がるほかに、手指の常在菌が原因で起こる食中毒もありますので、こまめな手洗いが重要です。
- 調理前・調理中にはしっかり手洗いを行う(つけない)
- おにぎりなどを握るときは、素手ではなくラップや使い捨てビニール手袋を使う(つけない)
味付け程度の塩分濃度では殺菌作用は期待できません。 - 生ものを扱った手、まな板や包丁などの調理器具で生食する野菜等を調理しない(つけない)
生食用食品を先に調理する、または洗浄・消毒殺菌を行ってから切り替えるようにしましょう。 - 調理台で生ものと生食用食材を近くに置かない(つけない)
- 下ごしらえから加熱調理まで間が開くときは冷蔵庫で保管する(ふやさない)
- 加熱調理では中心部まで火を通す(殺菌する)
食材の中心が75℃・1分以上までしっかり加熱されると食中毒を防ぐ目安になります。(ノロウイルス予防では、85℃以上が目安になります。)
料理用中心温度系があると、食材の内部の温度がわかって便利です。
盛り付けから保存まで
空気中にも細菌は存在するうえ、加熱でも完全には死滅しない種類もあります。
しっかり加熱した料理でも注意して取り扱いましょう。
- 出来上がったものは長時間放置せず、なるべくはやく食べる(つけない・ふやさない)
- 残ったものを保存するときは清潔な容器に入れて冷蔵または冷凍保存する
熱い状態の料理は少量ずつ分けることで温度が下がりやすく、細菌の繁殖しやすい温度帯を短時間で通過できます。
保存したものを食べるとき

作り置きは注意して行っていた場合でも、念押しの加熱や状態の確認は食中毒予防に重要です。
- 保存したものを温めなおすときは、再度しっかりと加熱する(殺菌する)
- 少しでも「あやしいな」と思ったときは、食べない選択をとる
まとめ
食中毒は命にかかわることもある危険なものです。
食事づくりにおける予防対策はもちろん、腹痛や下痢、嘔吐などで食中毒が疑われるときは放置せず、医療機関を早めに受診しましょう。
食中毒のうち発生件数の多いカンピロバクター食中毒について詳しく解説した記事はこちら
【消費カロリー管理に便利】スマートウォッチのおすすめ商品ランキングのページはこちら
【おすすめ】健康管理にも!おすすめ空気清浄機のご紹介
空気清浄機のおすすめ商品ランキングのページはこちら
|
参考文献 |