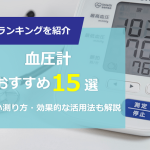近年は健康志向の高まりから、塩分に気を付けているという人も増えてきています。
塩分(ナトリウム、食塩)は人体に必須の栄養素のひとつではあるものの、取りすぎはさまざまな健康リスクを高める原因になることが知られています。
この記事では、食事の塩分が気になる方に向けて、健康を害さない一日あたりの塩分摂取量の目安と、塩分の過剰摂取による健康リスクを解説します。
身近な料理に含まれる塩分量と、手軽に始められる減塩のコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
Contents
塩分(食塩)の摂取基準値と実際の摂取量

塩分は摂りすぎてはいけないことは知っていても、具体的に摂っていいのはどれくらいまでなのか、明確な数値を知っている人は少ないのではないでしょうか?
1日あたりの塩分の摂取量について、世界の基準と日本の基準を日本人の現在の平均摂取量とあわせて紹介します。
WHOの目標値
WHO(世界保健機関)が発表している食塩摂取についてのガイドライン*1)では、成人において1日の食塩摂取量を5g未満に減らすことを強く推奨しています。
塩分の取りすぎは日本だけでなく世界的な健康課題の一つとされており、WHOの目標値は高血圧や心血管疾患のリスクを減少させることを目的として設定されています。
日本人の食事摂取基準2020年版での目標値
一方、日本国内での食塩の基準はどうなっているでしょうか?
日本人の健康の保持増進・生活習慣病予防のための栄養素等の摂取量の基準を示した「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、18歳以上の目標量として男性7.5g未満 女性6.5g未満という数値が設定されています。
WHOの基準値よりもやや緩い設定となっているのは、日本人の習慣的な摂取量から考えるとWHOの基準を目標値として設定するのは現実的ではない…との観点から。
「日本人は世界基準よりも多くとってよい」というわけではないことに気を付けたいですね。
日本人の食塩摂取量が減少していくにつれ、日本人の食事摂取基準における目標量もWHOの数値に近づいていくと予想されます。
(現に、日本人の食塩摂取量はやや減少健康にあり、食事摂取基準の改定のたびに目標量は小さくなっていっています)
現在の日本人の摂取状況
平成30年度の国民健康・栄養調査によると、私たち日本人の1日あたりの食塩摂取量は20歳以上の男性で平均11.0g、20歳以上の女性で平均9.3gとなっています。
また、国民健康・栄養調査とは異なる方法で20歳以上の日本人の食塩摂取量を推定した研究*2)では、1日あたり男性は14g、女性は11gもの食塩をとっていることが推定されました。
(国民健康・栄養調査は食事内容から食塩摂取量を算出、この研究は尿中ナトリウム排出量から摂取量を推定という違いがあります)
いずれにしても、日本人の習慣的な食塩の摂取量はWHOの推奨値よりもかなり多いことが分かります。
塩分取りすぎに関連する病気

とりすぎが問題視されている食塩(ナトリウム)ですが、食塩をとりすぎることは、私たちの健康に対して悪影響があることが分かっています。
具体的には以下のような疾病が挙げられます。
- 肥満・メタボリックシンドローム
- 高血圧、心血管疾患、腎臓病
- 胃がん
それぞれの内容について詳しく解説します。
肥満・メタボリックシンドローム
食塩摂取量と肥満との関係を調べた研究では、塩分を多くとる人ほど肥満の割合が高いこと*3)が報告されています。
肥満は高血圧や脂質異常症、糖尿病などの原因にもなり、様々な病気のリスクを高める要素のひとつです。
ダイエットの面だけでなく、健康の面でも、食塩は控えめに抑えるべきといえます。
高血圧、心血管疾患、腎臓病
食塩の過剰摂取は、高血圧を引き起こす原因のひとつです。
高血圧は、血管内の圧力が上がり血管内部にダメージを与えることで血管を破れやすく、詰まりやすくする「生活習慣病」です。
高血圧が進行すると全身の血管に負担をかけ、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まります。
(高血圧以外に内臓脂肪型肥満、血糖高値や脂質異常を併せ持ったメタボリックシンドロームの場合、さらにリスクが高くなります)
また、高血圧は腎臓にも負担をかけることから、食塩の過剰摂取は慢性腎臓病などの発症や重症化にかかわっている可能性が示されています。
胃がん
1日あたりの食塩摂取量とは別に、塩漬けの食品などの塩分の高い食品の摂取量が増えると胃がんのリスクを高めることが示されています。
がん予防の観点からも、食塩の過剰摂取、塩分の高い食品の過剰摂取には注意が必要です。
身近な料理の塩分量

私たちが口に入れる食塩の多くは料理の中に溶け込んでおり、目で見てその量を把握することは不可能に近いことです。
まずは、身近な料理に含まれる塩分量を知り、減塩を意識することから始めてみませんか?
いくつかの料理について、1食あたりの塩分量を紹介します。
| 料理名 | 1食分の分量(例) | 塩分量 |
| キムチ | 40g | 0.9g |
| みそ汁 | 汁150ml | 1.2g |
| カレーライス | 550g | 3.3g |
| ミートソーススパゲティ | 460g | 3.4g |
| 親子丼 | 500g | 4.0g |
| ラーメン | 麺・具300g+スープ400ml | 6.3g |
*女子栄養大学出版部. 5訂増補 調理のためのベーシックデータ. 女子栄養大学出版部, 2009 より作成
1日にとっていい食塩の量を5gと仮定すると、現代の食事では、1食の食事でも5gに近い量、または5gを超える量をとってしまいやすいようです。
もちろん、家庭やお店ごとの味付け・量の違いにより塩分量に違いは出ますが、普段の食事には思った以上に食塩が多く含まれていることが分かります。
特にどんぶりものやラーメンのような汁のある麺料理で塩分が高くなりやすいため、減塩のためには食べる頻度をあまり高くしないよう気を付けたいですね。
始めやすい減塩のコツ

減塩、とはいっても、何から始めて良いかわからないという人も多いのではないでしょうか?
食塩は調味料に多く含まれますが、単純に調味料の使用量を減らすだけでは食事の味が損なわれ、減塩がうまくいかない場合も。
始めやすく、負担の少ない減塩のコツを紹介します。
後がけ調味料は味見をしてから必要か決める
食卓で「食べるときに足す」調味料は実際の味の濃さよりも習慣でつけている人が多いところでもあります。
- 刺身・寿司の醤油
- 餃子のたれ
- 揚げ物のソース
- その他ケチャップ、塩など
まずは一口食べて味を見てから、卓上調味料は必要な分だけつけることを意識してみましょう。
また、「かける」よりも「つける」ほうが塩分摂取量は少なく済むことが知られています。
麺類のスープは飲み干さない
麺類のスープは他の汁物よりも塩分が多めになっており、減塩の視点では、なるべく控えめにしたいものになります。
- ラーメン
- そば
- うどん
これらの料理のスープはなるべく残す、加えて食べる頻度も控えめにできると、減塩に効果ありです。
栄養成分表示をチェックする

塩分の摂取量を減らすことが望ましいとはいえ、自分で調理・味付けをしない外食やコンビニなどで食事を用意する場合には、味付けを薄味に…という工夫がしにくいのが難点です。
加工食品をはじめ、コンビニのお弁当・お惣菜などなど、いろいろな食品に表示されている「栄養成分表示」で塩分量を確認してみましょう。
外食メニューでは表示されていないことも多いですが、コンビニなどで手に入る個別包装された食品にはほぼ確実に記載されているので、食塩量の把握に役立ちます。
食事を選ぶときは「食塩相当量」が1食あたり2.5g未満になるように選ぶようにすると、食事摂取基準の目標値にかなり近づけることができます。
だし、酸味、スパイス、ハーブをきかせる

うま味、酸味、香味野菜、スパイス、ハーブ類をきかせた料理は塩味が少なくてもおいしく食べられることが知られています。
- うま味…かつおぶし、こんぶ、干ししいたけ、肉類、魚介類などのだし
- 酸味…酢、柑橘類の果汁
- 香味野菜、ハーブ…しそ、生姜、にんにく、三つ葉、バジルなど
- スパイス…とうがらし、コショウ、カレー粉、山椒、七味唐辛子、花椒など
料理を作る場合には、塩分を控えつつ、これらの食材を取り入れたメニューにしてみてはいかがでしょうか?
市販の減塩調味料を活用する
近年は多くの調味料類に減塩商品がみられるようになってきました。
以下の市販調味料では減塩タイプを手に入れることができます。
- 醤油
- ソース
- 味噌
- 顆粒だし
- ドレッシング
- ケチャップ
これらの調味料はいつもと同じ感覚で使っても自然と減塩になるので、卓上の調味料にするのもオススメです。
ナトリウムの排出を促すカリウムを摂取する

カリウムはナトリウムの排出を促すミネラルです。
カリウムは様々な食品に含まれる栄養素ですが、カロリーのとりすぎを避けながらカリウムをたっぷりとるためには、野菜や果物などの重さあたりのエネルギーが低い食品がおすすめ。
食塩の摂取量には気を付けつつ、野菜や果物の摂取量を増やしていきたいですね。
まとめ
1日にとっていい食塩の量は意外に少なく、私たちは食塩をとりすぎる傾向があるようです。
食事は毎日の習慣のひとつであり、急に変えるのは負担が大きくなってしまいます。
無理のない範囲で、少しずつ改善を目指していきたいですね。
カリウムと高血圧の関係について詳しく解説した記事はこちら
特定健康診査・特定保健指導について詳しく解説したサイトはこちら
【おすすめ】生活習慣病予防に!高血圧・血圧高めを指摘されたら血圧計の活用がおすすめです!
【消費カロリー管理に便利】スマートウォッチのおすすめ商品ランキングのページはこちら
血圧計のおすすめ商品ランキングのページはこちら
|
参考文献 1*)WHO. Guideline: sodium intake for adults and children(2012) 厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会」 報告書 *2)Keiko Asakura, Ken Uechi, Yuki Sasaki, Shizuko Masayasu and Satoshi Sasaki. Estimation of sodium and potassium intakes assessed by two 24 h urine collections in healthy Japanese adults: a nationwide study British Journal of Nutrition Volume 112, Issue 7 14 October 2014 , pp. 1195-1205 *3)Long Zhou, Jeremiah Stamler, Queenie Chan, Linda Van Horn, Martha L Daviglus, Alan R Dyer, Katsuyuki Miura, Nagako Okuda, Yangfeng Wu, Hirotsugu Ueshima, Paul Elliott, Liancheng Zhao, INTERMAP Research Group, Salt intake and prevalence of overweight/obesity in Japan, China, the United Kingdom, and the United States: the INTERMAP Study, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 110, Issue 1, July 2019, Pages 34–40 女子栄養大学出版部. 5訂増補 調理のためのベーシックデータ. 女子栄養大学出版部, 2009 |