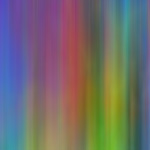理想の体を手に入れるためのダイエット。
しかし、現在の体型は人それぞれ違いますよね。
スタート地点が違えば目的への道も違ってきます。
まずは、自分のダイエットの目的と、自分のカラダについて再確認してみましょう。
【おすすめ】ダイエット中の経過チェックに最適!体重計・体組成計をご紹介
Contents
ダイエットとは
「ダイエット」という言葉の本当の意味をご存知でしょうか。
広く日本では「痩せること、体重を減らすこと」だと感じる方が多いですが、もともとは「美容や健康維持のため、食事の量・内容を決めること」を指します。
食事制限というと普段食べているよりも少なくするイメージがありますが、そうではなく、食事の量・内容について適切な範囲を設定し、日々の食事をその範囲に合わせることを指します。
食事の管理によって体重や体脂肪を減らすだけではなく、その人の体型や健康状態によっては体重や体脂肪を増やすことも含まれます。
あなたのダイエットの目的は?

ダイエットの目的は人それぞれですが、ダイエットの目的となるものは大きく分けて
- 健康のため
- 美容のため
が挙げられます。
健康維持のため
太りすぎていたり、やせすぎたりしていると、健康に影響があるのはよく知られています。
近年の日本では肥満による健康への影響が心配されていますが、やせすぎることによっても健康へのリスクが高まります。
|
■肥満による健康障害
|
|
■やせによる健康障害
|
このような、太りすぎ・やせすぎによる健康障害を防ぐために、食事の管理と適切な運動を行うのが健康のためのダイエットといえます。
美容のため
男女を問わず、メディアに登場するモデルやアイドルのすらっとした体型にあこがれる人は多いですよね。
モデル体型のような「みんな/自分がきれいと思う体型」に自分の体型を近づけたいと考えて行うのが美容のためのダイエットと言えます。
体重だけが美しさではない
とはいえ、やみくもに痩せた体は必ずしもきれいだとは言えない場合もあります。
体重が軽くても、やせすぎで骨ばっていたり、栄養状態が悪く肌が荒れていたり、顔色が悪かったりしていては台無しです。
もちろん、やせたことによって病的な状態に陥るのは論外です。
目指すのは健康的なカラダ
目指したいのは、適度に筋肉と脂肪のついた、健康的な体。
そのためには、体重の増減だけではなく、健康を意識しながらの食事の管理や運動の実践が必要です。
美容は健康の上に成り立つことを前提に、健康的なダイエットをしたいですね。
自分のカラダの現状を知る

現在の自分にダイエットは必要でしょうか?
BMIと体脂肪率から、現在の自分にダイエットが必要か、考えてみましょう。
BMIで判断する
肥満度の基準に、BMIというものがあります。
Body Mass Indexの略で、日本語ではボディマス指数といいます。
体重と身長から肥満度を表す体格指数で、体重(kg)を身長(m)の2乗で割って計算します。
BMI=体重(㎏)÷身長(m)2
日本肥満学会ではBMI22を、統計的に最も病気にかかりにくい体重として、標準体重と示しています。
| 状態 | 指標(BMI) |
| 低体重(やせ型) | 18.5未満 |
| 普通体重 | 18.5以上25未満 |
| 肥満(1度) | 25以上30未満 |
| 肥満(2度) | 30以上35未満 |
| 肥満(3度) | 35以上40未満 |
| 肥満(4度) | 40以上 |
※横スクロールで表全体の確認が可能です。
ただし、BMIは単に身長と体重から算出されるもので、体脂肪率や筋肉量などは計算に入っていません。
同じBMIの数値だったとしても、体組成によって人それぞれ異なる体型になりうることがあります。
【おすすめ】ダイエット中に必須の体重チェックには体組成計が最適です!
体脂肪率で判断する
最近は体脂肪計や体組成計などを利用して、家庭でも体脂肪率が測定できるようになりました。
体脂肪率による体型の分類は男女によって基準が異なります。
| 男性 | 女性 | |
| やせ(低い) | 15%未満 | 20%未満 |
| 普通(標準) | 15~20% | 20~25% |
| 肥満(高い) | 20%以上 | 25%以上 |
※横スクロールで表全体の確認が可能です。
BMIが肥満でも、体脂肪率が普通ややせの基準になる人は、筋肉量が多く、いわゆるがっちり体型といえるでしょう。
また、BMIがやせでも、体脂肪率が肥満の基準に入っている人は、隠れ肥満ともいわれ、体質的には肥満による生活習慣病などの健康障害が起こりうると考えられます。
BMIと体脂肪率を組み合わせて考える
| 体脂肪率 | 高い | 隠れ肥満 | 軽肥満 | 肥満 | |
| 標準 | やせ | 普通 | アスリート体型 (筋肉による体重が多い) |
||
| 低い | |||||
| 低体重 | 標準 | 肥満 (Ⅰ度) |
肥満 (Ⅱ度以上) |
||
| BMI値 | |||||
※横スクロールで表全体の確認が可能です。
上記の基準を自分の身長と体重・体脂肪率に当てはめてみて、いかがでしょうか?
やせ~普通~アスリート体型
痩せ体型・普通体型・アスリート体型の人は、体脂肪の量にはあまり問題はないと考えられます。
よって、ダイエットの必要性は低めです。
健康を維持するために、日常生活に必要な程度の筋肉を維持することを目標に食事の管理や運動を適度に行うことが大事といえます。
隠れ肥満体型
隠れ肥満体型にあたる人では、筋肉量の維持と増加がポイントです。
もともとの体質のほか、食事制限のみのダイエットなどを行うと、脂肪以外の成分も減ってしまい、隠れ肥満になりやすい傾向があり、リバウンドもしやすくなっています。
適切な食事に加えて適度な運動を行うと、脂肪が減って筋肉が増えることで外見がより引き締まって見えるうえ、太りにくい体を作ることができます。
軽肥満体型
軽肥満体型の人は、食事の見直しと運動によるカロリー消費がおすすめです。
体脂肪を減少させることによって体脂肪率、BMI値ともに減少させることができます。
バランスの良い食事で摂取カロリーを抑えつつ、運動で消費カロリーを増やしましょう。
肥満体型
肥満体型に当てはまった人は、必要に応じて専門家のサポートがおすすめです。
軽肥満タイプと同様、食事と運動で体脂肪を減少させましょう。
将来の生活習慣病予防と体にあった減量のためにも、医師の診察を受けることが望ましいでしょう。
目標の数値・ペースを設定する
ダイエットが必要!となれば、まずは成功させるための計画が大事です。
ダイエットの前に、減らしたい体脂肪の量・ペースを設定しましょう。
1㎏でも見た目は変わる
1㎏の体脂肪の体積は、1.1Lに相当し、500mlのペットボトル2本+100mlの小瓶のエナジードリンク1本分ほどあり、体脂肪1㎏の減少だけでもかなり引き締まって見えるのではないでしょうか。
ちなみに、1㎏分の筋肉の体積は0.9Lに相当し、同じ1㎏でも脂肪に比べて200ml少なく、紙パックジュース1本分ほどの違いが出ることになります。
健康的なペースは1か月1~2㎏まで
体調不良を起こさず、健康的に痩せていくには、1ヵ月に1~2㎏の減少にとどめ、なるべく継続していくことがおすすめです。
例えば、今より5㎏体脂肪を落としたい場合、3か月~半年で5㎏程度が適度なペースといえるでしょう。
ひと月あたりに減らしたい体重が決まったら、日ごろの食事と運動の目安を決めることができます。
記録と確認を習慣にしよう
体脂肪の増減は緩やかなため、なかなか実感しにくいかもしれません。
ダイエット前の自分の体を写真に収めておくと、どのくらい変わったのかを確認でき、モチベーションの維持にもつながります。
体型の変化を確認しつつ、必要に応じて目標を設定しなおすのもいいでしょう。
変化が実感できたら、体型の維持も目標になりえます。
どんなダイエット方法にも共通するダイエットの原則についての記事はこちら
食事・運動で体脂肪を落とす基本的なしくみについての記事はこちら
【消費カロリー管理に便利】スマートウォッチのおすすめ商品ランキングのページはこちら
【おすすめ】ダイエット中に必須の体重チェックには体組成計が最適です!
体重計・体組成計のおすすめ商品ランキングのページはこちら
|
参考文献 吉田勉 監修:「わかりやすい食品機能栄養学」.三共出版,2010. CLUB Panasonic:「BMI・タイプ別ダイエットのポイント」 国立健康・栄養研究所:「筋肉が1㎏増したとき、基礎代謝量は何kcal増すのか? |