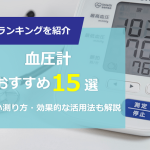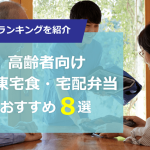腎臓は体内の老廃物の濾過を通じて全身の健康状態を保つ重要な臓器です。
腎臓病などにより腎臓の働きが悪くなると、腎臓に負担を掛けないような食事にするよう注意が必要です。
この記事では、腎臓病の食事療法を始める方向けに、腎臓病の概要と治療のために必要な食事のポイントについて、医師監修のもと管理栄養士が解説します。
積極的に活用したい食べ物、腎臓病の方におすすめのメニューのレシピも紹介しますので、腎臓病の方やご家族の方はぜひ活用してください。
腎臓病とは

腎臓病は腎臓の機能に障害を引き起こす病気を指します。腎臓の機能が徐々に低下する病気を「慢性腎臓病(CKD)」といいます。
腎臓は体内の老廃物の排出、体内の水分量の調節にかかわる臓器であるため、腎臓の機能が低下すると排出すべき老廃物が体内に残り続けてしまったり、体内水分量がコントロールできなくなったりしてしまいます。進行すると血液透析などで腎臓の働きを医療的に補う必要が出てくることもあります。
また、慢性腎臓病は貧血、骨粗鬆症、心血管疾患など他の健康問題のリスクを高めることがあります。
腎臓病の初期症状
初期の状態では自覚症状はほとんどありませんが、進行すると
- 疲労感
- むくみ
- 尿量の変化
- 高血圧
といった症状が現れることがあります。
腎臓病の重症度
慢性腎臓病の重症度は腎機能低下の原因となった原疾患、GFR(糸球体濾過量)区分、たんぱく尿区分を組み合わせて判断します。

NOBUヘルシーライフ内科クリニック:「急性腎障害(急性腎不全)・慢性腎臓病(CKD)」より引用
糸球体濾過量低下とたんぱく尿の度合いが高いほど重症度が高くなり、
- 死亡
- 末期腎不全
- 心血管死発症
といった疾患のリスクが高くなります。
GFR区分がG5になるまで腎機能が低下すると、透析や移植が必要になります。
腎機能は一度低下すると回復が難しいとされています。
慢性腎臓病の進行を遅らせ、腎機能をできるだけ長く維持するためには、適切な治療が重要です。腎臓病の治療には、食事療法、生活習慣の改善、薬物療法がありますが、ここからは食事療法についてご説明します
>>慢性腎臓病の概要と重症度判定、治療方法について詳しくはこちら
腎臓病の食事療法の基本

腎臓病の食事療法では、腎臓を強くするという考え方ではなく、腎臓に負担を掛けないようにし、病状の悪化を防ぐ意味があります。
具体的には、以下の栄養素等について管理を行います。
- 塩分(ナトリウム)
- たんぱく質
- カリウム
- カロリー
それぞれの内容について詳しく解説します。
塩分制限
高血圧は腎機能の低下を加速させるため、塩分の取りすぎを避けることが必要です。
慢性腎臓病における食事療法の一つとして、塩分制限が非常に重要な位置を占めます。
その理由は、塩分の過剰摂取は高血圧を引き起こす原因となり、高血圧は腎臓病の進行を加速させる危険因子となることにあります。
慢性腎臓病患者は、一般的に1日あたりの塩分摂取量を3~6g以下に制限することが推奨されています。ただし、患者の病状や体質によっては、さらに厳しい制限が必要となる場合もあります。
塩分といえば、調味料としての食塩をイメージするかもしれませんが、実際には食塩そのものだけでなく、加工食品や外食などでの隠れた塩分も多く摂取されています。
そのため、日常の食事全般での塩分摂取量を意識的に減らす必要があります。
食塩を多く含む料理の例として、味噌汁などの汁物、漬物類、乾物などが挙げられます。
日常的に摂取する食品でも高い塩分が含まれている場合が少なくないので、食事の選択や摂取量に気をつけることが求められます。
たんぱく質制限
たんぱく質の過剰摂取は腎臓への負担となるため、適切な摂取量を守ることが重要です。
具体的には、病状の進行度に応じた体重当たりのたんぱく質摂取の基準値に合わせた食事内容とします。
たんぱく質を摂取すると、体内で代謝されて尿素などの窒素排泄物が生成されます。
正常な腎臓では、これらの物質は効率的に排泄されますが、腎臓の排泄機能が低下しているとこれらの物質が体内に蓄積します。
その結果、さらなる腎機能の低下やその他の健康問題を引き起こす可能性が高まります。
そのため、慢性腎臓病の患者においては、適切な量のたんぱく質摂取が推奨されます。
具体的には、腎臓病のステージにより、標準体重1㎏に対して0.8~1.0g/日、または0.6~0.8g/日など、体格に応じた制限内容になります。
また、摂取するたんぱく質の質にも注意が必要です。
高品質のたんぱく質(例:魚、鶏肉、豆腐など)を選ぶことで、必要なアミノ酸を確保しつつ、腎臓への負担を最小限に抑えることができます。
カリウム制限
腎機能が低下すると、カリウムの排泄が低下するため、高カリウム食の制限が必要になる場合があります。
カリウムは心臓や筋肉の正常な機能の維持に必要な栄養素ではあるものの、血中にカリウムが増えすぎると不整脈や心停止の原因になることがあります。
慢性腎臓病では、血中のカリウムが増えすぎないように、食事から摂取するカリウムの量を管理する場合があります。
カリウムは幅広い食品に含まれますが、特にカリウムを多く含む食品として代表的なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 野菜類
- 果物類
- 豆、ナッツ類
- チョコレート、ココア
- 乳製品
これらの食品の摂取量や頻度を減らすことで、カリウムの過剰摂取を防ぐことができます。
ただし、カリウムの摂取をゼロにするわけではなく、必要な量のカリウムを確保しつつ、過剰摂取を避けるバランスが大切です。
適切なカロリー摂取
慢性腎臓病の患者における食事療法は、単に塩分やたんぱく質、カリウムの制限だけでなく、適切なカロリー管理も非常に重要です。
たんぱく質の制限を行うとカロリー不足のリスクが高まります。筋肉量の維持や健康状態の維持のために、十分なカロリー摂取が必要となります。
一方、過剰にカロリーをとりすぎると体重増加の原因となり、糖尿病や高血圧など、腎臓病の危険因子が増加してしまいます。
また、カロリーの摂取源の内容も重要で、中でも脂質に関しては、腎臓病と関連する心血管疾患のリスクを低減するため、不飽和脂肪酸を中心とする脂質が適していると考えられています。
腎臓病に良い食べ物とは?
腎臓病の食事療法は通常の食事と異なる部分も多く、腎臓病の食事療法を行いながら満足感のある食事をとることが難しい場合も少なくありません。
食べると腎臓の機能が改善するという食べ物はありませんが、腎臓病の進行を抑えるための食事療法の後押しになる食べ物を活用することで、腎臓病の食事療法を負担なく進めることが期待できます。
ここからは、腎臓病の食事療法を行っている方におすすめしたい食べ物を紹介します。
食塩を含まない調味料・減塩調味料

腎臓病の食事療法において食塩の摂取制限は重要なポイントのひとつです。
しかし、減塩を行うと食事が味気なくなってしまうことから、減塩がうまくいかないということも少なくありません。
そこで、食塩を含まない調味料や、通常よりも食塩を減らした調味料を活用することで、食事をおいしく食べながらも、減塩を成功させることが可能です。
■食塩を含まない調味料の例
- だし(こんぶ、かつお節、干しシイタケ、貝類など)(※顆粒は食塩を含むので注意)
- 酢(米酢、穀物酢、りんご酢など)
- 柑橘類(レモン、ゆず、かぼす、すだちなど)
また、減塩調味料として、通常のものよりも少ない食塩量になっているものも多く流通しています。
■減塩タイプが販売されている調味料の例
- 醤油
- 味噌
- ソース類
- ドレッシング
- ケチャップ
- ポン酢
- 顆粒だし
ただし、減塩タイプの調味料の場合、通常よりもカリウムが多く含まれている場合がありますので、カリウム制限がある方の場合には主治医や管理栄養士等に相談してから活用するようにすると安心です。
香味野菜・ハーブ・スパイス

食塩を含まない調味料と並んで食事の満足感を高めるのに有効なのが、香味野菜やハーブ、スパイスといった食材です。
これらは基本的に食塩を含まないうえ、料理に風味を持たせてくれるため、食塩の使用量が少なくても満足しやすくなります。
■香味野菜、ハーブ、スパイスの例
- 生姜
- にんにく
- 大葉
- バジル
- コショウ
- カレー粉
- トウガラシ
- わさび
チューブ入りのにんにく・生姜や一部のスパイスには食塩の含まれたものもありますので、購入する際には原材料や栄養成分表示を確認し、食塩の含まれないものを選ぶようにしましょう。
適量のたんぱく質

腎臓病において、たんぱく質の取りすぎは腎臓の負担を高めるため、たんぱく質制限が行われる場合があります。
しかし、たんぱく質を過剰に制限すると低栄養などのリスクがあることからも、適量のたんぱく質を摂ることが重要です。
たんぱく質の摂取源としては、アミノ酸スコアの高い以下の食品がおすすめです。
アミノ酸スコアの高いこれらの食品は必須アミノ酸を豊富に含むため、体に必要なアミノ酸(たんぱく質の構成成分)を効率的に摂取することができます。
- 肉類
- 魚類
- たまご
- 乳製品
- 大豆製品
また、腎臓病の進行を抑えるという意味では、十分なたんぱく質を含みつつも、リンが少なく、不飽和脂肪酸の多い食材がより適しています。
- 鶏肉
- 豚肉
- 卵白
- 青魚(さば、いわし、アジなど)
- 大豆製品(豆腐など)
鶏・豚・魚の場合、脂身の多い部位は重さあたりのたんぱく質が少なく脂質が多いため、たんぱく質摂取量を抑えつつカロリーや食べた時のボリューム感を増すのに適しています。
ただし、たんぱく質制限の度合いは病状によっても異なるため、具体的な食材の選択や摂取量については、主治医等と相談しながら進めるのが安心です。
カロリー源となる適量の糖質・脂質

カロリー源となる栄養素にはたんぱく質、脂質、糖質があります。
しかし、腎臓病でたんぱく質制限を行っている場合、体に必要なカロリーの確保が難しくなることがあります。
そのため、腎臓病では、必要なカロリーを確保するための適量の糖質・脂質の摂取が必要です。
- 穀類(米、パン、麺類)
- 青魚(さば、いわし、アジなど)
- 植物由来の油脂(サラダオイル、菜種油、オリーブオイルなど)
上記の食品は、カロリー源としての糖質や脂質を含みつつ、以下のような腎臓病の食事療法に適した栄養素が含まれる食品となっています。
- 食物繊維の摂取源となる
- 不飽和脂肪酸の割合が高い
このうち、穀類と魚に関してはたんぱく質も含んでいるため、取り入れる際にはたんぱく質制限の内容を考慮する必要があります。
腎臓病の病者用食品

一般に販売されている加工食品の中には、腎臓病の方が食べるのに適した内容のものが「病者用食品」として、消費者庁の表示許可を受けて販売されています。
消費者庁が表示許可を出している腎臓病に関する病者用食品は主に以下の2種類。
加えて、個別評価を受けたものも販売されています。
- 低たんぱく質食品
- 腎臓病用組み合わせ食品
具体的には、以下のような食品が腎臓病病者用食品として存在します。
- レトルトごはん
- 乾麺
- 粉乳
- 冷凍宅配おかずセット
いずれの場合も使用に際しては医師や管理栄養士に相談の上使用するのが原則ですが、上手に活用することで、食事療法の負担を少なくできます。
腎臓病において食べてもいい果物とは?
果物は野菜と同様にカリウムを多く含む食品であること、さらに生で食べることが多いため、カリウムを流出させにくい事などから、腎臓病の食事療法では避けられがちな食品といえます。
いっぽうで、果物は食物繊維やビタミンなどの必須栄養素の摂取源になる食品でもあり、取り入れるメリットもないわけではありません。
そのため、果物に関しては、一律に食べられる・食べられないではなく、自分の体の状態に合ったものを適量範囲で取り入れることが大切です。
果物や野菜の摂取量の制限が必要かどうか、具体的にどの種類の果物をどのように食べるか、という事については、腎機能低下の度合いによっても異なり、腎臓病だからと言って全員に同じ線引きを行うことはできません。
必ず主治医や管理栄養士と相談したうえで食事内容を決定し、その枠組みの中で取り入れるようにしましょう。
果物に注意が必要な場合には、果物の中でも重さあたりのカリウムが比較的少ないものを選んだり、カリウムを減らす調理法を行うことで、腎臓への負担を少なくすることができます。
■重さあたりのカリウムが比較的少ない果物の例
- ブルーベリー(生)…70㎎/100g
- りんご(皮むき・生)…120㎎/100g
- みかん(早生・じょうのう・生)…130㎎/100g
- ぶどう(皮むき・生)…130㎎/100g
■重さあたりのカリウムが比較的多い果物の例
- アボカド(生)…590㎎/100g
- バナナ(生)…360㎎/100g
- メロン(生)…340㎎/100g
- キウイフルーツ(緑または黄・生)…300㎎/100g
■カリウムを減らす調理法の例
- カットした後水にさらす
- カットした後茹でこぼし、シロップで煮る(コンポート)
腎臓病に良い食べ物レシピ
腎臓病で食事に制限のある方におすすめのレシピを紹介します。
50~64歳男性、平均的な身長で腎臓病のステージがG3bの場合を想定して考案しました。
※腎臓病における食事療法の内容は腎機能のステージや原疾患によっても異なります。
実際に食べる食事に関しては、主治医や管理栄養士に相談の上、自身の身体状況に適した内容にする必要があります。
ごま醤油だれと香味野菜で食べる豚しゃぶサラダ

分量(1人分)
- 豚バラ肉薄切り…50g
- レタス…20g
- きゅうり…20g
- トマト… 20g
- しそ…1g(1枚)
- みょうが…5g(1/2個)
- 減塩醤油…10g(大さじ1/2強)
- 砂糖…12g(大さじ1)
- 酢…7.5g(大さじ1/2)
- すりごま…5g(小さじ1)
- ごま油…2g(小さじ1/2)
作り方
レタスは1cm幅の細切り、きゅうりは縦半分に切って1㎜厚の斜め薄切り、シソは千切りにし、それぞれ水にさらす。
トマトは食べやすい大きさに切り、みょうがは斜め薄切りにする。
たれの材料を全て混ぜて小皿に移しておく。
鍋にたっぷりのお湯を沸かし、豚バラ肉をさっとゆで、水にとる。
皿に野菜を盛り、豚肉を乗せる。タレを付けて食べる。
栄養価
- カロリー…298kcal
- タンパク質…9.5g
- 脂質…22.5g
- 炭水化物…16.7g
- 食物繊維…1.4g
- 食塩相当量…0.9g
- カリウム…308㎎
- リン…129㎎
ポイント
たんぱく質の割合が低くカロリーが取れる豚バラ肉を用い、薄切りにしてゆでることでカリウムを流出させて少なくすることができます。
野菜類も同様に、カットした後に水にさらすことで、カリウム量を減らせます。
シソやみょうがといった香味野菜を用い、ごま油、酢など風味のある調味料を組み合わせることで、減塩しつつ満足感のある味わいになるようにしました。
すりごまはタレをつくる際にいりゴマをすって作ると香りが立ってさらに深みのある味わいに仕上げることができておすすめです。
腎臓病で注意したいこと

腎臓病の治療や食事療法に関して、インターネットやメディア上で様々な情報が氾濫しており、目に届きやすい状態になっていますが、その情報すべてが正しいもの、というわけではありません。
腎臓病になってしまったときに、できるだけ腎臓の機能を保ち、健康な生活を維持するために注意すべきことについて解説します。
腎臓病を治す・強くする食べ物はない
腎臓病の食事療法について、「腎臓病を治す食べ物」や「腎機能を回復させる食材」を探す人は少なくありませんが、実際には腎臓病を直接治すような食べ物は存在していません。
腎臓病の食事療法では、「腎臓にプラスの影響を与える食品を選ぶ」ではなく、「腎臓にかかる負担が少ない食品を選ぶ」といった方向で考えられています。
これは、「病状の進行を遅らせる」「症状を軽減する」ことが目的であり、腎臓病を治すものではないということを意識する必要があります。
一般に「腎臓によい食べ物」として紹介されるものでも、とればとるだけよいというものはありません。
食事全体のバランスを考慮したうえで有用なもの、という認識を持っておくと安心です。
自己流の食事療法は避ける
腎臓病の食事療法を行うにあたって、自己流で行うことは絶対に避けましょう。
一般的に健康的といわれる食事内容でも、腎臓病においてはそうでないことが多くあるため、食材の選定ひとつをとっても、専門的な知識で取捨選択する必要があります。
また、腎臓病とひとくくりに考えることはできず、ほかの腎臓病患者に適した食事が自分にも適しているとは限りません。
腎臓病は腎機能のレベルに応じて複数のステージに分けられていることに加えて、原疾患の違いなどにより、食事制限の内容に大きな差が生じます。
個々人の持つさまざまな要因を組み合わせて考える必要があることから、自己流で適切な食事内容を判断することは困難です。
間違った食事療法を続けることで、かえって腎臓への負荷が高まり、体調の悪化やほかの健康問題につながることも考えられます。
専門医・管理栄養士の指導を受ける
腎臓によい食事をとることについて、最も重要なのが「専門医や管理栄養士の指導を受けながら行う」ということです。
専門医や管理栄養士は、その人の腎機能のレベル、合併症の有無、その他の要因から、個別に最適の食事バランスを提案することができます。
また、過去の臨床データや最新の研究内容に基づいた情報を提供してくれるため、自己流で行う食事療法のリスクを減らすことができます。
また、食事内容や検査値などを客観的に判断し、的確なアドバイスを継続的に行ってくれるため、適切な食事内容の継続につながりやすく、長期的な健康維持に役立ちます。
腎臓病の食事療法について患者本人や家族等の近しい関係の人が理解を深めることは重要ですが、具体的な内容について決定するのは、専門家であると安心です。
まとめ
腎臓病は様々な要因で腎臓の機能が低下した状態であり、腎臓の負担を減らすような食事内容が求められます。
病状によっても内容や程度は異なりますが、食塩、たんぱく質、カリウム、リンを控える食事内容が推奨されます。
ただし、腎臓病は人によって状況が大きく異なり、制限が必要な栄養素の種類やその量についても、個人ごとに内容に違いがあります。
自己流の食事療法はリスクが大きいため、必ず医師・管理栄養士の指導の下で行うようにしましょう。
適切な治療・食事療法を受けるには、腎臓病の専門医に相談をするのがおすすめです。
自宅での血圧管理に。血圧計のおすすめ商品ランキングのページはこちら
|
参考文献 厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会」 報告書 文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 |
監修医師
| 医院名 | NOBUヘルシーライフ内科クリニック |
|---|---|
| 院長名 | 藤原 信治 |
| 資格 | ・医学博士 ・日本内科学会認定 総合内科専門医 ・日本糖尿病協会認定 療養専門医・指導医 ・日本腎臓病学会認定 腎臓指導医 ・日本透析医学会認定 透析専門医・指導医 ・日本循環器学会認定 循環器専門医 ・厚生労働省認定 難病指定医 |