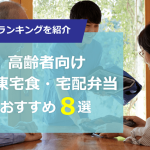腎機能低下で通院される患者さんから、よく『腎臓病で食べてはいけないものは何ですか?』という質問を受けることが多いとお聞きしました。
そこで、今回の記事では、腎臓病の食事療法を行っている人に向けて、「腎臓病で食べてはいけないもの」、正確には「摂取制限が必要な食べ物」を、医師監修のもと管理栄養士が解説します。
毎日の食事療法をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてみてくださいね。
Contents
腎臓病で避けるべき食品とは?

腎臓病の食事療法では、腎臓の機能維持のために食塩やたんぱく質、場合によってカリウムやリンといった特定の栄養素が制限されます。
これらの栄養素が特に多く含まれる食品は腎臓病の食事療法の妨げになりやすいものであるため、摂取を控えるか、医師や管理栄養士の指導のもと、注意しながら摂取する必要があります。
腎臓病の食事療法において注意が必要な食品について、具体例を挙げながら紹介します。
食塩を多く含む食品

食塩を多く含む食品は少量でも1日の食塩摂取量に影響しやすく、注意が必要なものといえます。
実際の塩分量ととりすぎないためのポイントを紹介します。
しょうゆやソースなど卓上調味料
調味料類は食塩を多く含んでいることがほとんどです。
特に、食卓で食事をとるときにしょうゆやソースなどをそれぞれの好みに応じて使うことがありますが、こういった卓上調味料は使用量が把握しにくく、ついついとりすぎてしまうことも珍しくありません。
■卓上で使うことの多い調味料に含まれる食塩の量
| 食品名 | 1回量(目安) | 食塩相当量 |
| 食塩 | ひとつまみ(1g) | 1.0g |
| こいくちしょうゆ | 大さじ1(18g) | 2.6g |
| 中濃ソース | 大さじ1(18g) | 1.0g |
| 和風ドレッシング | 大さじ1(15g) | 1.1g |
| こいくちしょうゆ(減塩) | 大さじ1(18g) | 1.5g |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
卓上調味料からの塩分の取りすぎを防ぐためには、以下のような方法が考えられます。
- 調理作業内で味付けを完結し、卓上調味料は使わない
- 計量しながら利用する
- 料理に直接かけるのではなく、小皿などにとってつけて食べる
- 減塩タイプに切り替える
いちどに食塩摂取量を減らすのは難しいので、上記の工夫を実践しながら、徐々に薄味になれていくようにしましょう。
汁物・麺類のスープ
普段食べる料理の中でも、汁物や麺類のスープは私たちが思うより多くの塩分を含んでいます。
そのため、汁物や麺類のスープを飲む量や頻度が多いと、塩分摂取量を増やす原因のひとつとなります。
■汁物や麵類のスープに含まれる塩分量(目安)
| 料理名 | 1人分(目安) | 食塩相当量 |
| みそ汁 | 150ml | 1.2g |
| うどんつゆ | 260ml | 2.5g |
| 野菜タンメン | 400ml | 3.5g |
五訂増補 調理のためのベーシックデータ. 女子栄養大学出版部, 2009.6 より作成
これらの食品からの塩分摂取量を減らすには、以下のような方法が挙げられます。
- みそ汁などの汁物は1日1回までにする(制限内容に応じて調整が必要)
- 麺類のスープは飲まずに残す
汁物やスープ入りの麺類は1杯でも塩分の摂取量が多くなりがちですので、見直すことで塩分摂取量を大幅に抑えることが可能です。
高塩分の漬物・干物など
食塩は食品の保存性を高める作用があることから、さまざまな加工品に使用されています。
特に、漬物や干物などには高塩分のものが多く、少量でも塩分摂取量を増やしてしまいます。
■漬物・干物等に含まれる塩分量(目安)
| 料理名 | 1人分(目安) | 食塩相当量 |
| たくあん | 25g | 0.6g |
| キムチ | 40g | 0.9g |
| 梅干し(塩漬けタイプ) | 10g | 1.8g |
| 塩昆布 | 5g | 0.9g |
| アジ干物 | 80g | 1.4g |
| たらこ | 10g | 0.5g |
五訂増補 調理のためのベーシックデータ. 女子栄養大学出版部, 2009.6 より作成
漬物や干物など食塩を使用した加工品はごはんが進むものが多くなっていますが、食塩の摂取量を抑えるためには、以下のような工夫が必要になります。
- 漬物、干物は1日1回1種類までにする
- 1回の摂取量をあらかじめ計算しておく
- ほかの料理の塩分量を抑え、メリハリをつける
- 減塩タイプがあれば活用する
1回の摂取量の少なさから、漬け物類は必須栄養素の摂取源にもなりにくいため、比較的なくしても栄養上の問題が起こりにくい部分ですので、積極的に見直したいポイントです。
カリウムを多く含む食品

腎臓病でカリウム制限もある場合、血中カリウム濃度を抑えるためにも、カリウムを多く含む食品に注意する必要があります。
カリウムはさまざまな食品に広く含まれる栄養素ですが、特に野菜と果物は他の食品と比較して1回あたりの摂取量が多くなりやすいため、注意が必要です。
野菜
野菜は一般的に健康に良い食品として扱われますが、腎臓病の場合、カリウムをとりすぎないように注意が必要な食品です。
その一方で野菜は食物繊維やビタミンの摂取源でもあるため、カリウム以外の栄養素摂取とのバランスを欠かないよう、医師や管理栄養士の指導を受けながら選択していくことが大事です。
■カリウムを多く含む野菜
| 食品名 | 100gあたりのカリウム |
| ほうれんそう | 690㎎ |
| えだまめ | 590㎎ |
| モロヘイヤ | 530㎎ |
| たけのこ | 520㎎ |
| 小松菜 | 500㎎ |
| 水菜 | 480㎎ |
| ブロッコリー | 460㎎ |
| 春菊 | 460㎎ |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
野菜のカリウムを減らす方法としては、生食ではなく、断面が多くなるようにカットして茹でこぼしてから使うなどの方法があります。
果物
果物は野菜と比較すると、平均的にカリウムの含有量は控えめですが、生のまま食べること・ドライマンゴーやレーズンのような乾燥品で食べることが多く、カリウムが流出する機会が少ないために摂取量が増えやすいことに注意が必要です。
■カリウムを多く含む果物
| 食品名 | 100gあたりのカリウム |
| ドライマンゴー | 1100㎎ |
| レーズン | 740㎎ |
| アボカド | 590㎎ |
| バナナ | 360㎎ |
| メロン | 350㎎ |
| キウイフルーツ | 300㎎ |
| さくらんぼ(米国産) | 260㎎ |
| ぶどう(皮つき) | 220㎎ |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
果物は野菜と異なり、茹でこぼすといったカリウムを減らせる調理が行いにくいのが難点。
一方で野菜と同様にビタミンや食物繊維の摂取源となるものなので、専門家の指導のもと管理していく必要があります。
たんぱく質を多く含む食品

腎臓病では腎臓の負担を抑えるため、食事からのたんぱく質摂取に注意が必要です。
ただし、たんぱく質は体の筋量の維持などにも重要な役目を果たすため、病状に応じた適量を摂取することが重要です。
肉、魚、卵、大豆製品、乳製品は体が必要とするたんぱく質の効率的な摂取に役立つ一方、たんぱく質の摂取量自体も増やしやすいので、摂取量に気を配る必要があります。
肉類
肉類はたんぱく質を多く含む食品の代表格といえます。
皮を取り除いた鶏肉や、脂身の少ない「赤身部位」になるほど、重さあたりのたんぱく質の含有量が多くなります。
■たんぱく質を多く含む肉類
| 食品名 | 100gあたりのたんぱく質 |
| 鶏ささみ | 24.6g |
| 鶏むね(皮なし) | 24.4g |
| 手羽先(皮つき) | 23.0g |
| 豚肉(ヒレ) | 22.7g |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
ただし、重さあたりのたんぱく質が多いほど体に悪い、と単純に考えることはできず、たんぱく質に対するリンや飽和脂肪酸の量を考慮する必要がありますので、食事療法を行う際には主治医や管理栄養士の指導を受けるようにしてください。
魚介類
魚介類も肉類と同様、脂身の少ない魚種・部位になるほどたんぱく質の含有量が高くなります。
また、魚介類では乾燥品や塩蔵品も多くなるため、重さあたりのたんぱく質含有量が高くなっているものも少なくありません。
■たんぱく質を多く含む魚介類
| 食品名 | 100gあたりのたんぱく質 |
| しらす干し | 40.5g |
| いくら | 32.6g |
| くろまぐろ赤身 | 26.4g |
| びんちょうまぐろ | 26.0g |
| かつお | 25.8g |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
魚介類も肉類と同様、たんぱく質が多いほど良くないと単純に考えることができません。
医師や管理栄養士に相談の上食事療法を行うようにしましょう。
卵類
卵は肉類・魚介類と比較すると重さあたりのたんぱく質量は控えめですが、摂取頻度が高くなりやすいことから注意が必要な食品といえます。
卵黄と卵白で比べると卵黄に比較的多く、鶏卵とうずら卵を比べるとうずらの卵でたんぱく質が多くなっています。
■たんぱく質を多く含む卵類
| 食品名 | 100gあたりのたんぱく質 |
| 鶏卵(卵黄) | 16.5g |
| うずら卵 | 12.6g |
| 鶏卵(全卵) | 12.2g |
| 鶏卵(卵白) | 10.1g |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
中でも卵黄はたんぱく質だけでなくリンも多く含んでいます。
手軽なことからとりすぎにもつながりやすいので、意識する必要がある食品といえるでしょう。
大豆製品
大豆製品は植物性食品の中でもたんぱく質を多く含む食品として知られています。
飽和脂肪酸が少なく、食物繊維が取れるなどの利点もあるものの、制限内容によっては注意すべき食品のひとつとなります。
日本の食生活では大豆製品を多用しがちですので、医師や管理栄養士と相談を進めながら、無理なく管理していきたいですね。
■たんぱく質を多く含む大豆製品
| 食品名 | 100gあたりのたんぱく質 |
| きな粉 | 37.5g |
| 煎り大豆 | 37.5g |
| 納豆 | 16.5g |
| ゆで大豆 | 14.8g |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
乳製品
乳製品には牛乳由来のたんぱく質が含まれており、加工によって濃縮されていることが多くなっています。
特にチーズ類は塩分も多く含むことが少なくありませんので、注意が必要な食品のひとつといえるでしょう。
■たんぱく質を多く含む乳製品
| 食品名 | 100gあたりのたんぱく質 |
| パルメザンチーズ | 44.0g |
| ゴーダチーズ | 25.8g |
| チェダーチーズ | 25.7g |
| プロセスチーズ | 22.7g |
| カマンベールチーズ | 19.1g |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
リンを多く含む食品

腎臓病では血中のリン濃度が高くなりやすく、骨の健康を害するリスクが高まることから、病状に応じて制限が必要になります。
リンは食品添加物として使用されていることがあり、加工品で多くなりやすい特徴があります。
加工食品
乳類・大豆類の加工品で含有量の高さが目立ちます。
たんぱく質も多く含む食品が多いため、併せての注意が必要なものといえます。
■リンを多く含む加工食品
| 食品名 | 100gあたりのリン |
| パルメザンチーズ | 850㎎ |
| 高野豆腐 | 820㎎ |
| プロセスチーズ | 730㎎ |
| 煎り大豆 | 710㎎ |
| きな粉 | 660㎎ |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
海産物の乾物
リンを多く含む食品として、海産物を乾燥させた製品が挙げられます。
1回の摂取量はさほど多くないものの、重さあたりのリンが多いことに加え、食塩やたんぱく質が濃縮されていることから、腎臓病の食事療法を行っている人には向かない食品といえます。
■リンを多く含む魚介類
| 食品名 | 100gあたりのリン |
| 煮干し(カタクチイワシ) | 1500㎎ |
| 干しさくらえび | 1200㎎ |
| スルメイカ | 1100㎎ |
| しらす干し | 860㎎ |
| かつお削り節 | 680㎎ |
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 より作成
まとめ
腎機能低下の患者さんが、『食べてはいけないもの』ではなく、『摂取制限が必要なもの』としてご説明しました。
ただし、腎臓病(腎機能低下)は患者さんの病状によってもそれぞれ内容や程度が異なります。
食塩、たんぱく質、カリウム、リンの摂取を控える度合いは、詳しい検査を受け、医師・管理栄養士の指導の下で実施していく必要があり、適切な治療・食事療法を受けるには、腎臓病の専門医療機関を受診し、相談をするのがおすすめです。
自宅での血圧管理に。血圧計のおすすめ商品ランキングのページはこちら
|
参考文献 厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会」 報告書 文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 五訂増補 調理のためのベーシックデータ. 女子栄養大学出版部, 2009.6 |
監修医師
| 医院名 | NOBUヘルシーライフ内科クリニック |
|---|---|
| 院長名 | 藤原 信治 |
| 資格 | ・医学博士 ・日本内科学会認定 総合内科専門医 ・日本糖尿病協会認定 療養専門医・指導医 ・日本腎臓病学会認定 腎臓指導医 ・日本透析医学会認定 透析専門医・指導医 ・日本循環器学会認定 循環器専門医 ・厚生労働省認定 難病指定医 |